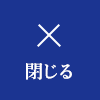児童手当
児童手当とは
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している方に支給する制度です。
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度の内容が変わりました。詳しくは、こちらのページでご案内しています。
(重要)制度改正に伴う申請について
令和7年3月31日(月曜日)までは申請を受け付けます。その場合、令和6年10月分以降の拡充分の手当を、遅れて申請した月の翌月を目安にまとめて支給します。ただし、書類の不備があった場合や申請のタイミングによっては翌々月の支給となります。
令和7年4月1日(火曜日)以降に申請した場合は、申請した月の翌月分から支給を開始します。この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できません。
児童手当を受けられる人
児童手当は、広川町内に住所があり、18歳に到達後の最初の3月31日までの児童を養育している方に支給します。
(1)父母が共に児童を養育している場合は、原則として生計を維持する程度の高い方(原則所得の高い方)が受給者となります。
(2)児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給されます。
(3)未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。
「未成年後見人」・・・未成年者に対して親権を行う者がない時など、親権を行い、子の監護・教育等に関し、親権者と同様の権利義務を有する者
「父母指定者」・・・例えば、児童の父または母が海外に居住しており、児童は祖父母と国内で同居しているような場合、父または母が祖父母のいずれかを「父母指定者」に指定することにより、祖父母に児童手当を支給します。
(4)要件を満たす方が複数いる場合は、児童と同居している方に支給します(単身赴任等の場合を除く)。
(5)公務員の方は、勤務先から支給されます。
手当月額
対象となる児童1人につき、以下の表の年齢区分等に応じて支給されます。
| 年齢区分 | 一人当たりの月額 |
|---|---|
| 0歳から3歳未満(第1子・第2子) | 15,000円 |
| 0歳からから3歳未満(第3子以降) | 30,000円 |
| 3歳以上から高校生年代(第1子・第2子) | 10,000円 |
| 3歳以上から高校生年代(第3子以降) | 30,000円 |
(1)申請のあった月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転入日等の翌日から15日以内に申請すれば出生・転入等の日の属する月の翌月分から支給を受けることができます。
(2)第1子、第2子などの数え方は、22歳に到達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの養育する子(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち年長者から、第1子、第2子・・・と数えます。進学・就職・婚姻・出産等に関わらず、請求者(受給者)が当該子を養育していれば、算定の対象になります。就職等により、自立して生活している(養育していない)場合は、算定の対象外です。
(注)所得制限・所得上限
令和6年10月分(令和6年12月支払分)の児童手当から、所得制限及び所得上限は撤廃されました。ただし、所得更正で過年度分の所得が下がった場合など、過去に遡って児童手当が支給される場合、令和6年9月分以前の手当については所得制限(上限)が適用されます。
手当支払
手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
なお、児童手当は、原則として、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の10日(10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の休日等ではない日)に、支払月の前2か月分の手当を受給者名義の金融機関の口座に振込みます。
手続きについて
以下の手続きについて、子ども課こどもまんなか係窓口にて受付けます。
(1)出生や転入等により新たに児童手当を受給する場合
認定請求書が提出された翌月分から児童手当は支給されます。
ただし、出生日や転入日等の翌日から15日以内に申請すれば出生・転入等の日の属する月の翌月分から支給を受けることができます。
例1 7月30日に出生し、8月14日に申請(15日以内) → 8月分から支給
例2 7月30日に出生し、8月15日に申請(15日より後) → 9月分から支給
【申請に必要なものなど】
- 請求者名義の普通預金通帳(キャッシュカードも可)
- マイナンバーの確認に必要なもの
- 本人確認書類(免許証等)
- 請求者の現在、加入している年金について加入状況が確認できない等の場合に、請求者の健康保険証、年金加入証明書、資格確認書、医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」、またはマイナポータル画面で確認いたします。
【該当者のみ必要となる書類】
| 対象者 | 必要書類 |
|---|---|
| 児童と別居している方 |
※別居監護申立書(記入例)(PDFファイル:123.6KB) |
| 配偶者からの暴力等により、住民票に住所地以外にお住まいの方 | ・児童手当等の受給資格に係る申立書(DV) |
| 支給要件児童の戸籍や住民票がない方 | ・戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書 |
| 離婚協議中で夫婦が別居し、児童と同居している方 |
・児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母) ・協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本 |
| 父母以外の方(祖父母等)が請求者となる場合 | ・監護生計維持申立書 |
| 未成年後見人が請求者となる場合 | ・児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人) ・児童の戸籍謄本 |
| 請求者が海外にいる父母等によって指定された方となる場合 | ・父母指定者届 |
| 児童が海外留学している場合 | ・児童手当に係る海外留学に関する申立書 ・留学先の在学証明書と翻訳書 |
※(注)各申立書の様式は、子ども課にあります。上記以外にも書類が必要となる場合もがありますので、詳しくは、子ども課こどもまんなか係へご相談ください。
(2)第2子以降の出生等により児童手当が増額になる場合
申請のあった翌月分から児童手当は支給されます。ただし、出生日の翌日から15日以内に申請すれば出生の日の属する月の翌月分から支給を受けることができます。
【必要書類等】
- 請求者の本人確認書類
(3)その他の届出
次の事由に該当するときは速やかに届出をしてください。
| 届出が必要な主な事由 | |
|---|---|
| 監護要件等がなくなったことにより支給対象となる児童が減ったとき(手当の額が減るとき) | |
| 監護要件等がなくなったことにより支給対象となる児童がいなくなったとき(手当の支給が終わるとき) | |
| 受給者や配偶者、児童の住所・氏名等が変更となったとき | |
| 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき | |
| 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき | |
| 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育している場合に限る) | |
| 受給者名義の振込口座を変更するとき | |
| 受給者がお亡くなりになったとき | |
| 毎年6月頃に郵送する「現況届」が届いたとき(6月中の申請となります) | |
| 受給者が公務員になったとき または受給者が公務員でなくなったとき |
|
| 受給者が市外へ転出したとき |
(注)届出によって必要書類等が異なりますので、詳しくは子ども課にお問い合わせください
現況届について
令和4年度(2022年度)から、一部の方を除き、現況届の提出は不要です。
現況届の提出が必要な方には、毎年6月上旬に受給者の住所宛に郵送します。
この現況届により受給資格を確認しますので、児童手当を継続して受給するために6月中に必ず提出してください。
なお、現況届の提出が必要な方で提出がない場合は、8月支払い(6月から7月分)以降の手当の支給が一時差止になりますのでご注意ください。
(注)児童手当の受給にあたり、届出している内容に変更が生じた場合は、変更の届出等が必要です。
| 現況届の提出が必要な方 |
|---|
| 配偶者と離婚協議中につき、支給要件児童を連れて配偶者と別居している方 |
| 配偶者等からの暴力(DV)により、住民票を異動せずに支給要件児童を連れて避難している方 |
| 戸籍及び住民票に記載のない支給要件児童(無戸籍)を養育している方 |
| 未成年後見人として支給要件児童を養育している方 |
| 申請者自身のお子様でない子を養育している方 |
| 受給者と支給要件児童が住民票上別居している方(一部除く) |
| 進学せず就職等した子(就職(進学)浪人含む)を継続して養育している方 |
| 児童養護施設等の設置者および里親の方 |
| その他、広川町から提出の案内があった方 |
高校・短期大学・専門学校等を卒業後も継続して養育する場合の手続きについて
令和6年制度改正により、高校等を卒業した後も、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子(大学生年代まで)については、第3子以降の加算を計算する際の算定対象とすることができるようになりました。
(注)大学生年代の子自身は、児童手当の支給対象外です。
大学生年代以下の子を3人以上養育している(うち1名以上は高校生以下)方で、高校等を卒業した子について、卒業後も監護及び生計費の負担をし、第3子加算の算定対象とする場合は、以下の書類の提出が必要です。
2.「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:93.1KB)」
(記入例)
1.「額改定認定請求書(記入例)」(PDFファイル:162.4KB)
2.「監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)」(PDFファイル:128.3KB)
該当する方には広川町から案内を郵送いたしますので、案内が届きましたら期限までに申請してください。
(注)案内は2月下旬から3上旬頃に発送します。
(注)大学生年代以下の子を3人以上養育している(うち1名以上は高校生以下)、かつ、監護・生計費の負担をし、第3子加算の対象とする場合のみ申請が必要です。
(注)進学・就職・婚姻・出産等に関わらず、受給者が養育していれば申請の対象になります。就職等により、お子様が自立して生活し、経済的支援がない場合は、申請の対象外です。
公務員について
採用日(退職日や異動日)の翌日から起算して15日以内に申請してください。
申請が遅れると、手当を受給できない期間が生じたり、二重支給で過払いが発生したりすることがありますのでご注意ください。
広川町から児童手当を受給している方が、公務員として採用される場合
広川町から児童手当を受給している方が公務員になる場合、勤務する職場で申請を行い、児童手当を受給することになります。
広川町からの支給は終了となりますので、速やかに任用通知書をお持ちいただき、受給事由消滅届を提出してください。
(注)公務員でも、職場から児童手当が支給されない場合があります。職場から児童手当が支給されるかどうか、必ず事前に職場に確認してください。
職場から児童手当を受給している公務員の方が、退職等される場合
公務員である児童手当の受給者が退職・出向等により職場から児童手当を受給しなくなる場合、新たに住所地の市区町村で申請を行い、児童手当を受給することになります。速やかに消滅通知書をお持ちいただき、認定請求書を提出してください。
申請窓口
教育委員会事務局 子ども課 こどもまんなか推進室 こどもまんなか係
電話 0943-32-1194
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 子ども課 こどもまんなか推進室
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1194/ファクス:0943-32-4287
メールでのお問い合わせ