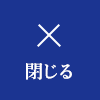みんなで広げよう「ワンヘルス」
ワンヘルス(One Health)とは、「人と動物の健康と環境の健全性は一つ」と捉え、これらを一体的に守ろうという考え方で、世界的にその取組が進められています。また、福岡県でもワンヘルスに関する課題を解決するための「6つの基本方針」や「ワンヘルス推進行動計画」が示されました。
広川町では福岡県の行動計画等に連携協力するとともに、町民への周知、ワンヘルス実践施策を推進する「ワンヘルス推進宣言」をしています。
広川町ワンヘルス推進宣言
新型コロナウイルス感染症をはじめとする人獣共通感染症は、森林開発などの土地利用の変化、これに伴う生態系の劣化や気候変動等によって人と野生動物の生息区域が変化したことで、動物の持つ病原体が人にも感染するようになったと言われています。
このような状況から人獣共通感染症に対応するために、人と動物の健康と環境の健全性を一つのものとして捉える「ワンヘルス」の理念のもと、総合的な取組みが求められています。
福岡県では、全国に先駆けて「福岡県ワンヘルス推進基本条例」を制定し、人と動物の健康及び環境の健全性を一体的に守るための6つの基本方針や行動計画を策定しました。
本町も、ワンヘルスの理念のもとに下記の事項に取り組み、ワンヘルスを推進することをここに宣言します。
記
1 ワンヘルス実践の基本方針を具体化する福岡県ワンヘルス推進行動計画に連携協力するとともに、ワンヘルス実践施策を推進します。
2 町民へのワンヘルスの周知に努め、理解の促進を図り、その実践活動に対し必要な支援を行います。
令和6年6月10日
広川町長 氷室 健太郎
広川町「ワンヘルス推進宣言」(PDFファイル:78.1KB)
詳しい内容は県ホームページをご覧ください。
6つの基本方針
1.人と動物の共通感染症対策
2.薬剤耐性菌対策
3. 環境保護
4. 人と動物の共生社会づくり
5. 健康づくり
6. 環境と人と動物のより良い関係づくり
1.人と動物の共通感染症対策
現在、⼈に感染する病原体は1,400種以上あり、その中には、新型コロナウイルス感染症など⼈と動物の共通感染症が多数あります。動物から人へ、人から動物へ感染する感染症を「人獣共通感染症」といい、人の感染症の約60%を占めると言われています。
感染を阻⽌するためには、1感染源、2感染経路、3宿主の3つに対するそれぞれの対策が必要であることから、⼈、動物、環境それぞれのアプローチによって⼈や動物の感染を防ぐことが重要です。
- 感染源
感染症の原因となる病原体を保有し、人や動物に感染させることができる動物や食べ物など。 - 感染経路
病原体が感染源から宿主へ移動する方法。感染している人のくしゃみや咳から感染する「飛沫感染」、手に付いた病原体が口などから入り感染する「接触感染」など。 - 宿主
病原体が体内に入って寄生や共生されることにより、体内で病原体が定着・増殖した生き物。
私たちができること
- 人獣共通感染症の発生予防とまん延防止のために、日頃から手洗いやうがい、咳エチケット等の基本的な感染防止対策を行いましょう。
- ペットと触れあったあとは手を洗う、草やぶなどに入る際は長袖・長ズボンを着用するなど、動物との適切な関わり方を理解し動物やダニなどからの感染に注意しましょう。
2.薬剤耐性菌対策
「薬剤耐性菌」とは、抗菌薬に対し抵抗性を獲得した細菌のことです。
細菌による感染症を発症した場合、抗菌薬を使用することが有効です。しかし服用量や期間などを守らないと、目的の細菌を死滅させることができないだけではなく、体内の他の細菌を死滅させ、抗菌薬に対して抵抗力(耐性)を獲得した「薬剤耐性菌」を発生させる原因となります。この薬剤耐性菌による感染症が発生した場合、これまで使用していた抗菌薬が効かなくなるなど、治療が困難となります。
今、「薬剤耐性菌」が増加する一方、新たな抗菌薬の開発が減少していることが世界的に問題となっています。また、抗菌薬は家畜などの動物にも使用されており、畜産現場でも「薬剤耐性菌」が発生し、環境への汚染や畜産物、農産物から人へ拡がることも問題となっています。
私たちができること
- 薬を正しく使用しましょう。
抗生物質の効かない薬剤耐性菌の発生を減らすため、処方された抗生物質は、途中で服用をやめず、用法用量を守り、最後まで飲み切りましょう。 - 薬剤耐性菌による感染症の一部は、動物から人、人から動物に感染することも確認されています。愛玩動物(ペット)が病気にならないように、日ごろからペットの健康にも気を配りましょう。
3.環境保護
近年のグローバル化や大量消費・大量生産は、人や動植物にとって貴重な森林や生態系を破壊し、気候変動の原因の一つとなっています。また、大規模な森林伐採や都市開発は、これまで、人間社会と触れ合う機会のなかった野生動物が持つ病原体と、人が遭遇するきっかけを作ったとされています。
自然環境は、人を含む様々な生物が生きる場です。生態系を守り、人と動物とのすみ分けが保たれてこそ、人と動物の健康を保つことができます。そして、健全で豊かな自然環境を次世代に引き継いでいかなければなりません。
私たちができること
- 福岡県が行っている生物や地球環境を保全する取り組みについて知りましょう。
- 地球温暖化対策として、二酸化炭素の排出を抑えるため、外出する際は自家用車ではなく、バスや電車などの公共交通機関を利用したり、自転車、徒歩で通勤通学をするよう心がけましょう。
また、環境に配慮した商品を率先して購入したり、地域の自然を保全するための地域活動に参加しましょう。
4.人と動物の共生社会づくり
犬や猫、鳥などの愛玩動物(ペット)は、私たちの生活に潤いや安らぎを与え、今や家族の一員となるほど重要な存在になっています。 また、災害救助やアニマルセラピーなど、私たちの社会活動の様々な場面で活躍する動物もいます。
このように人と動物が共生している一方で、不適切な飼育や虐待、遺棄等の問題、愛玩動物を介した共通感染症に感染する事例も発生しています。
人と動物との関係をより良く保つためには、動物のことをよく理解することが大切です。動物をペットとして飼う場合や社会で活用する場合は、正しい飼い方等を十分に知っておく必要があります。
私たちができること
- 飼っている動物には、予防接種や健康診断を受けさせ衛生管理に気を配り、寿命を迎えるまで適切に飼養しましょう。
- 野生動物に関する生態や行動、習性について理解を深め、一定の距離を保つ等適切に関わりましょう。
5.健康づくり
人の健康は、適度な運動習慣の定着や、食生活の改善といったことに加えて、人や動植物が心も体も健やかな状態で過ごすことができる生活環境において育むことができます。
例えば、豊かな自然の中を散歩したり、動植物と触れ合うことは、年齢や性別、障がいの有無に関わらず、人を元気にする力があります。
森林とふれあうことは、ストレスホルモンの減少や血圧の低下、脈拍数の減少、免疫機能の増強等の効果があることが科学的にも実証されています。
これからの健康づくりは、動植物や環境とのつながりを大事にしていく必要があります。
私たちができること
- スポーツ等の趣味を様々な形で楽しみ、調和のとれた自然環境と多様な動植物との関係の中で生活していきましょう。
- 愛玩動物とのふれあいを通じた健康づくりをしてみましょう。
6.環境と人と動物のより良い関係づくり
私たちの健康は、健全な環境で生産された健康な家畜や、安全な農作物・水産物などを食べることで維持されています。
そして、米や野菜等を作るには、健全な環境の農地や水が必要です。また、肉・卵・牛乳などの畜産物は牛・豚・鶏などが健康に育つよう、その飼育環境や餌の安全性に配慮しなければなりません。さらに、納豆やチーズなどの発酵食品は、乳酸菌やビフィズス菌などの微生物の働きで作られています。
このような「食」に対する知識を持ち、「何を食べるのか」「何を食べてはいけないのか」を学ぶ「食育」を通して、農作物・水産物が作られている環境について関心を持つことも大切なことの一つです。
私たちができること
- 「食」に対する知識を持ち、農林水産物が生産されている環境等へ関心を持ちましょう。
- 「食育」を通じて、食の安全・安心や環境への負荷の軽減にもつながる「地産地消」や農林水産物の理解を深めましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 生活環境係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1138/ファクス:0943-32-4287
メールでのお問い合わせ